今までに、本の紹介言うのはしたことがなかったと思いますが、ちょっと面白い本がありましたのでご紹介させて頂きます。
それがこの本です。
※アマゾンより
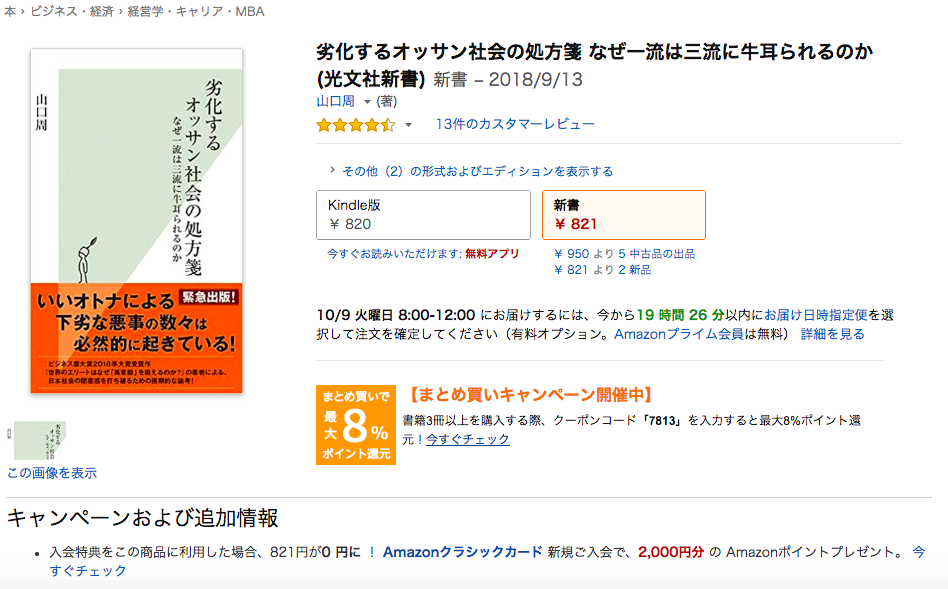
この本の解説が書かれているのですが、これが実にわかりやすい!その内容が下記になります。
2018年9月18日 形式:新書(Amazonで購入)
タイトルは一見ふざけているように感じるかもしれませんが、中身は非常に骨太です。個人や組織が劣化(いわゆる「オッサン化」)するメカニズムを明らかにし、現在の日本企業や社会で起きている現象の根本原因を解説するとともに、「オッサン化」しないための対策まで提示されています。
著者によれば、組織が劣化するのは以下のようなメカニズムによるものです。
明治維新や太平洋戦争の終結など、社会構造の転換が起きると、既得権を握っていた年長者が退場します。↓ 若手が重責を担い、自由に仕事ができる環境が整い、坂本龍馬や西郷隆盛、本田宗一郎、盛田昭夫、松下幸之助といった第一世代が登場します。↓ 彼らが掲げたアジェンダのもとで、優れた仕事経験を積む第二世代が育ちます。↓ しかし、人材選定に一定の確率でエラーが生じるため、徐々に凡人がリーダーに据えられ、第三世代が育たず、結果として組織が劣化していきます。
このサイクルは約80年単位で繰り返されるとされており、前回が1945年だったとすると、2025年はまさに「第三次ガラガラポン革命前夜」にあたります。今後、何をきっかけにこの「ガラガラポン」が起こるのか、注視していきたいと思わせられる内容です。
本書は個人にもフォーカスしており、企業におけるシニア人材活用のヒントや、25~50歳の「セカンドステージ」にいる人々にとって有益なアドバイスが多数詰まっています。また、著者は以前から「日本に必要なのは欧米型のリーダーシップではなく、サーバントリーダーシップだ」と語っていましたが、本書はその考えを正面から論じた初の書籍でもあります。
ただし残念な点もあります。それは、改善が必要な当のオッサンたちがタイトルを見ただけで「自分とは関係ない」と思い、本書を手に取らない可能性があることです(まさにそれが「オッサン化」の証左なのですが)。
以下は読書メモの抜粋です。
-
現在の50〜60代は、かつての「大きなモノガタリ」が喪失する以前に社会適応した最後の世代。社会や会社に対し「約束が違う」と不満を抱えていても不思議ではない。
-
昭和の「大きなモノガタリ」は、そこそこの大学を出て、そこそこの会社に入り、そこそこ頑張ればお金持ちになれて幸せになれるという物語だったが、それが崩壊し、代わってグローバル資本主義が支配的になった。
-
古い物語に適応した人々が、今も社会の上層部に居座って指示を出し、新しい物語に適応した人々が中下層でその指示を実行しているという歪んだ構造になっている。
-
世代交代を重ねるごとにリーダーの選定ミスが積み重なり、凡人が上に立つ確率が高まる。日本企業の多くは、採用活動を工場の資材調達のように処理しており、才人が関与していないため、組織の尖りが徐々に失われていくのは当然。
-
組織を自浄作用で立て直すのは困難であり、最もシンプルなのは一度破壊し、再構築する「革命」である。
-
権力者にプレッシャーを与える手段には「オピニオン(意見)」と「エグジット(退出)」がある。どちらもしないのは、権力者を支持しているということと同義。
-
日本企業の多くでは40代後半でキャリアの天井にぶつかる。社長は一人、役員も限られており、座席は少ない。
-
外資系企業が厳しいのは解雇があるからではなく、早い段階で「あなたはここまで」と伝えるだけ。むしろ若いうちに他の道を選べるのは有利。
-
「年長者は尊敬すべき」という命題は、変化の緩やかな時代には妥当だったが、激動の時代には過去の経験が逆に害となる場合もある。
-
株式会社は成長を求められる存在であるが、成長とは同時に組織の肥大化も意味し、硬直化を招く。
-
昔は情報が物理的な形に結びついていたため、必要な情報にアクセスするのは困難だったが、今は情報の普遍化が急速に進んでいる。
-
サーバントリーダーシップとは、権力に頼らず支援に徹するリーダー像。経験と権威に依存した支配型モデルとは真逆の考え方。
-
リーダーシップは個人の資質ではなく、関係性の中で生まれるものであり、「あの人にはリーダーシップがある」ではなく「周囲がリーダーシップを感じている」が正しい。
-
サーバントリーダーには圧倒的な能力は不要で、「懐の深さ」こそが求められる。若手の可能性を活かすには、これを支える存在が不可欠。
-
創造的な高齢者は、常に「人生のアジェンダ(課題)」を設定し、それをクリアするために日々学び続けている。
-
個人の成長には、職場での良い経験が決定的に重要。
-
経団連は、日本型社会システムの象徴的存在であり、採用ルールや副業制限などを一方的に指導し、圧力をかけているのは「談合」に等しい。
-
私たちは、年を取っただけで威張れない時代を初めて生きている。
-
ストレスがない状況では「チャレンジ」とは言えず、セカンドステージでの挑戦と失敗経験が、サードステージでの耐性を育てる。
-
これからの人生モデルは、「学び」と「働き」が並行して進む形が主流に。「学ぶ」ことこそ、真の意味での若さを保つ秘訣である。
ここ数年、日本企業では数多くの不正問題が発生していますが、それらの背景には、このレビューにあるような「組織の劣化構造」が関係しているように思えてなりません。そして、それは民間企業だけでなく、国家の中枢を担うキャリア官僚の間でも確実に起きており、遠くない将来、組織の劣化が原因となる「組織崩壊」が避けられなくなると確信しています。
だからこそ私は、日本円だけに依存するのではなく、「外貨での日本円ヘッジ」が今こそ必要であると考えています。
